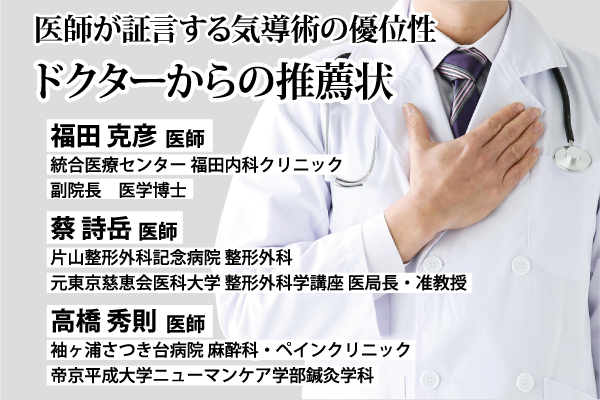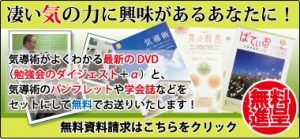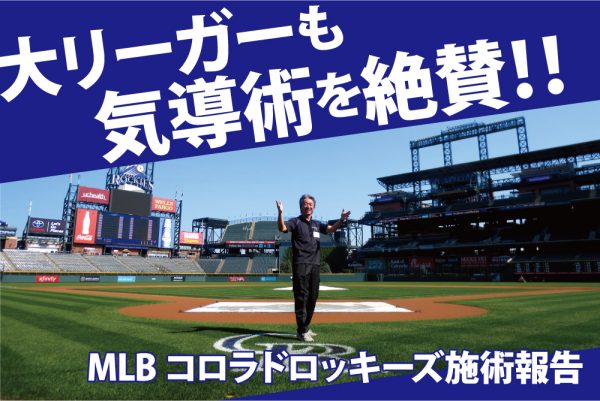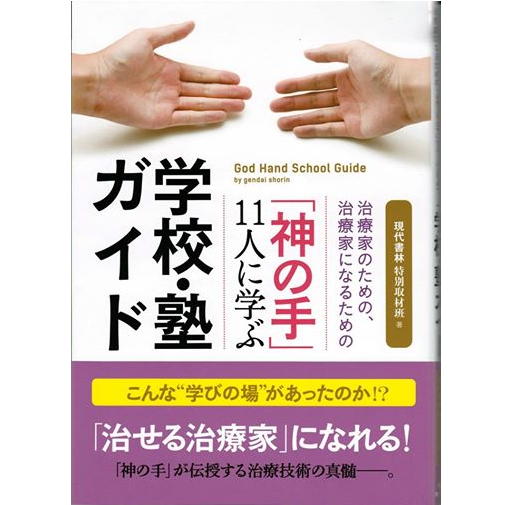【五反田校】フリーレクチャーⅡ・第5回
五反田校フリーレクチャーⅡクラスをご受講いただきました皆さま、ありがとうございました。
この『フリーレクチャーⅡ』コースも、参加者のご質問に応じてあなたが一番喜ぶ内容を展開していくクラスになります。知りたいも、上手くなりたいも、治してくださいも、全て対応いたします。
加えて、講師全員が皆さまにお伝えしたいテーマを必ずひとつは持ち寄り、皆さまのご要望があればレクチャーできるように準備して臨んでおります。
初心者からベテランまで、ぜひご参加ください。講師一同、気合い入っています!
したがって、A教室とB教室では展開される内容は当然異なりますし、その日にご参加いただいたメンバーによっても異なります。
それでは第5回のA教室とB教室のそれぞれでレクチャーされたテーマをご紹介いたします。
<A教室> 2025年10月4日(土)開催
○足首と股関節の可動域拡大を図る簡単調整法
・仙骨の正しい使い方の教育
・足首と股関節を正しく連動させる教育
・仙骨の正しい立て方の教育
(担当:鈴木本部長)
自身の足首の症状を治す方法、患者さんの足首や股関節の可動域を広げる方法、というお二人の方から出された質問。さらに、自身の足首を治したい方からは、子供の頃に友だちと競争した、しゃがんで歩く「でんでんむし」ができなくなっているので、またできるようになりたいという追加のリクエスト。この全てに共通するのは足首。本部長の診立ては、足首を単体としてうまく使えていないというのもあるが、脚自体をうまく使えていないというのが、原因のひとつとしてあるとのことでした。脚がうまく使えないのは、股関節と足首の連動性と仙骨のパワーの使い方がよろしくないからだということ。それを改善する、目から鱗のアプローチが紹介されました。
○脊柱起立筋の調整法
・皮膚と筋膜の滑走性を改善するアプローチ
・肩甲骨の上方回旋運動の活性アプローチ
(担当:三本木講師)
三本木講師が先月発表した多裂筋の調整法は、背中の中央部分が楽になるアプローチ。今回は、それより外方に移ったラインを楽にする脊柱起立筋の調整法が紹介されました。以前、第199回の研究実践コースで「背部の筋肉を活性して流れの良い背中を手に入れる」として発表されたアプローチの解釈を変えて応用した「皮膚と筋膜の滑走性を改善するアプローチ」と、オリジナルの「肩甲骨の上方回旋運動の活性アプローチ」の2手順で構成されています。
○体幹前面に溜まる腎臓の疲れの解消
・腎臓の疲れが溜まる体幹前面のポイント
・気導力の効力向上による効果の実感
(担当:大井講師)
過去、第198回研究実践コースで「腎と関連する体幹前面の圧痛を解消する」として発表されたアプローチ。私の中には「腎は元気の源」という考えが強く定着しているため、治療の際には腎臓の状態を重視する傾向があります。そのような理由で、腎臓ポイントがすごく硬かったり、恥骨際の圧痛が非常に強い人に対して、併せ取りアプローチとして以前は多用していました。しかし、アカシックワールドからの新テクニックによって、個々にアプローチしても各々充分解消できるので、最近は活用していませんでした。しかし、このアプローチは一手で全身を楽にできる効果があります。では、このアプローチに最新テクニックによる気導力注入を組み入れたら、その効果はどれだけ高まるのか!その高まった効果を皆さんに実感していただきました。
<B教室> 2025年10月11日(土)開催
○足がつる症状の改善法の一考察
・原因となる神経の栄養不足による機能低下
・腰椎の可動性のチェックと改善法
・腰椎の捻じれ解消アプローチ
・症状に関わる原因の探り方
・効果が及ぶ範囲の設定
・健側と比較しながらの調整
(担当:鈴木本部長)
受講生の方が、右足ばかりをよくつるということで、それを改善するアプローチが展開されました。まずは、足がつる原因の解説から始まり、左足と比較して右足の方が機能的に悪く感じるということで、筋力検査などによる状態確認が行われました。次に、腰椎の硬さをチェックしたところ非常に硬かったので、その原因を解消。この解消法は必見ですよ!さらに背中の歪みを、その原因を探りながら、自力を使わせるなどして調整していく、流れるようなアプローチが展開されました。自力を使わせる調整法も知っておきたいもの!ここで入った、知っておきたい解説がアプローチにおける重要な意識の持ち方。最後に、あお向けでの調整として、健側と比較しながらの調整法や押さえておきたい部位へのアプローチ、骨盤を前傾させる調整法が展開されました。最後の、骨盤を前傾させる調整法も必見です!!いつものことながら今回も、非常に勉強になる内容ばかりが盛りだくさんでした。
○腰部の多裂筋調整法
・ストレッチ効果も踏まえた多裂筋へのアプローチ
・多裂筋の活性アプローチ
(担当:三本木講師)
先月の胸椎部の多裂筋の調整法に続き、今月は腰部の多裂筋がターゲット。胸椎部の場合と同様に、多裂筋と起立筋へのストレッチ効果も踏まえたアプローチと、バストマットを活用して施す、腸腰筋の活性も視野に入れたオリジナルの腰部多裂筋の活性アプローチが紹介されました。
参加者のご要望にお応えする形で展開する『フリーレクチャーⅡ』コース。
これまで皆さまが気づかなかった実践的なニッチな情報をお伝えすることで、皆さまの知識の隙間が埋まって、皆さまの引き出しの中にある知識が有機的に繋がっていくような場にしたいと思います。
皆さま、これからの『フリーレクチャーⅡ』コースにぜひぜひご期待くださいませ!!!
※あらかじめテーマを決めて展開するセミナーではないのでレジメはございませんが、レクチャーの内容の要点を記した「セミナーメモ」がDVDに添えられます。
セミナーに参加できなかった皆さまは、ぜひDVDをご購入くださいませ。
大井 洋