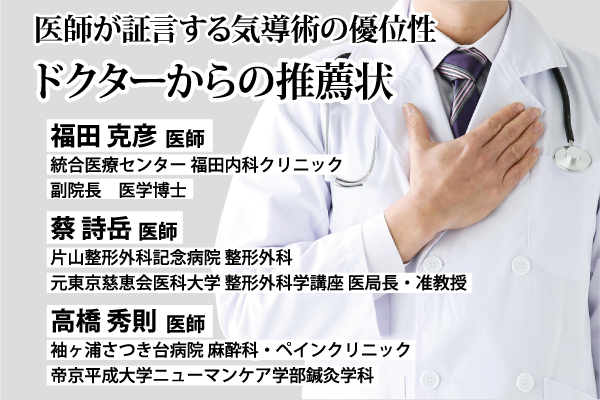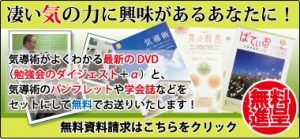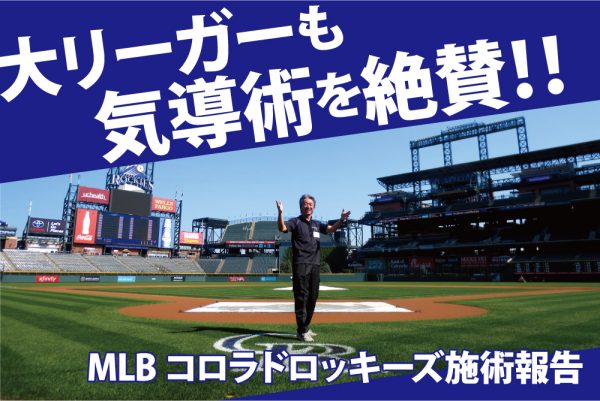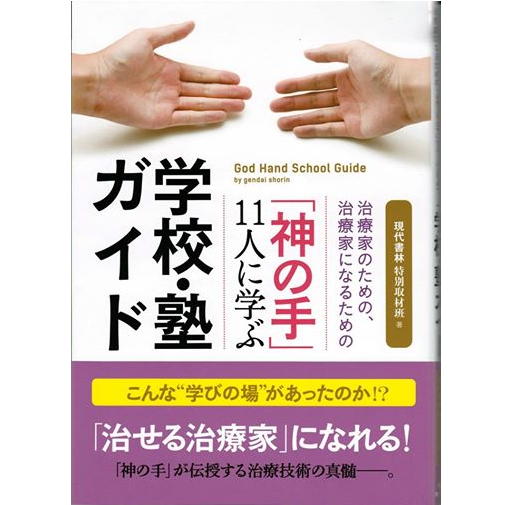【五反田校】フリーレクチャー2・第2回
五反田校フリーレクチャー2クラスをご受講いただきました皆さま、ありがとうございました。
この『フリーレクチャー2』コースも、参加者のご質問に応じてあなたが一番喜ぶ内容を展開していくクラスになります。知りたいも、上手くなりたいも、治してくださいも、全て対応いたします。
加えて、講師全員が皆さまにお伝えしたいテーマを必ずひとつは持ち寄り、皆さまのご要望があればレクチャーできるように準備して臨んでおります。
初心者からベテランまで、ぜひご参加ください。講師一同、気合い入っています!
したがって、A教室とB教室では展開される内容は当然異なりますし、その日にご参加いただいたメンバーによっても異なります。
それでは第2回のA教室とB教室のそれぞれでレクチャーされたテーマをご紹介いたします。
<A教室> 2025年7月5日(土)開催
○のぼせ症状に対するアプローチ
・のぼせ症状に該当する諸症状とのぼせ状態の解説
・のぼせ症状が生じる機序とその原因の診立て方
・のぼせる人が痛がるポイント(膻中・血海)
・腹部状態改善のためのふくらはぎ深部の状態改善
・体温調整や代謝促進のための肝腎テクニック
(担当:鈴木本部長)
すごく汗をかく、手足が冷える、寝つきが悪い、風呂に入るとのぼせる、など色々な形で現れるのぼせ症状。身体の中枢の血流が促進されて、手足にうまく巡っていないことで、気が上昇して、頭がポッポポッポしてしまうという状態です。一日中のぼせている人はいません。のぼせ症状は、環境や心境、時間の変化などに対して自律神経が調整を図ることによって、身体がシフトしなければいけないところを、身体の反応が追いつかずにうまく順応できないことで生じます。したがって、基本的なアプローチとしての「椎骨インプット」や「ストレス遮断」、「体温調整」はやることを前提にしての解説が展開されました。
のぼせ症状の場合にチェックしたいのが「膻中」と「血海」。加えて、のぼせ症状の人は呼吸が浅いので、呼吸の状態をチェックするのが重要とのこと。これらは色々と関係していて、腹式呼吸が苦手な人は「膻中」の圧痛が強く、それがお腹の硬さにも関係しているそうです。腹式呼吸を教育するに当たって、まずはお腹の硬さを改善するアプローチとして、のぼせ症状の人にこれもしばしば見られる「ふくらはぎの深部」の異常解消アプローチが解説されました。このアプローチが目から鱗の内容で、驚きと同時に非常に勉強させていただきました。皆さん、必見ですよ!
○膝が伸び切らない状態の改善法
・腸腰筋短縮の検査方法
・膝伸展動作を妨げる原因の解消
・膝の完全伸展に関わる半月板に付く筋肉の調整法
・膝関節の骨の摺り合わせ活性法
(担当:鈴木本部長)
立位で膝がしっかり伸びていないことで、膝蓋骨が動かない患者さんへの対応が質問されました。膝が伸びないという状況にも色々あり、寝ていれば膝は伸びるが立つと曲がってしまうというケースでは、腸腰筋が短縮していると考えられます。まずは、腸腰筋の短縮が明確にわかる検査法が紹介されました。その後展開された腸腰筋短縮改善のアプローチが、これもまた目から鱗の内容でした。腸腰筋の短縮は、単純に硬縮によって短縮しているばかりでなく、力が抜けない状態になっていることで生じているケースがあるとのこと。その原因のひとつが膝の状態。この場合、あおむけで寝た状態でも少し膝が曲がっています。膝を積極的に伸ばす動作にブレーキをかけている原因の解消から始まり、半月板に付着する筋肉の調整などの膝関節の調整法がとても分かりやすく解説されました。これも必見ですよ!
○烏口腕筋の関連ポイント
・烏口突起および烏口腕筋とハムストリングの関連
(担当:大井講師)
日頃治療をしていると、三角筋を緩めてもその前縁の奥に硬いものを触知することがよくあります。烏口腕筋の硬縮です。非常に小さな筋肉ですが、私はその硬縮は簡単には緩まないと感じていました。最近の患者さんで、動き出しなどに上腕の痺れと肩付け根辺りの胸部の気持ち悪さが生じるという80代の患者さんがいました。かなり手強い症状で、毎回楽になってお帰りになるのですが、ぶり返しがなくなるまでに7回の治療を要しました。あまり間を空けずに来院してもらい要所を改善していき、最後に決め手となったのが烏口腕筋。前回の治療で徹底的に緩めたのに、また硬縮していました。やはり動き出しで胸部の気持ち悪さがでるとのこと。ということは、下肢のどこかに烏口腕筋の関連ポイントがあるということ?そこで見つけたのがハムストリングでした。
○棘上筋の調整法
・ローテーターカフの構成と役割および関連する症状
・棘上筋の調整(弛緩→ストレッチ→活性)
(担当:三本木講師)
肩関節において、動きに伴って上腕骨頭を適切に引き付けて、動きをスムーズにする役割を担うローテーターカフ。三本木講師は今回、その中の「棘上筋」にフォーカスして、可動域の正常化と元気に働ける状態を求めた調整法を紹介しました。
<B教室> 2025年7月12日(土)開催
○咳症状改善の一考察
・様々な咳症状
・熱中症によるダメージの怖さ
・熱中症からの咳症状改善の複合的アプローチ
(担当:鈴木本部長)
身体の中から出ていくものに対しては、理由があって身体の中から出そうとする働きなので、闇雲に止めるというものではない。とは言っても、その中で咳というのは、ひど過ぎると消耗してしまい辛いものです。加えて、咳症状の場合は症状が長引いている理由が分からないケースがよくあるとのことです。
質問者の方は、熱中症の症状を感じた翌日から咳が出だしたとのこと。そこで、複合的なアプローチが解説されました。大きな呼吸をした時の咳の出方の確認や胸骨上縁(天突)を操作した時の反応から解説がスタート。咳の感受性や喉の炎症含めての絶対的な反応ポイントや咳き込んでいる人に圧痛が出る部位へのアプローチ、咳の反射ポイントの紹介など咳症状を改善するアプローチが解説されました。加えて熱中症に対するアプローチも解説されています。最後に、寝た状態の方が咳は出やすいので、あお向けでの咳の感受性の調整や咳の要因となっている症状を解消するアプローチが解説されました。
○中殿筋と小殿筋の調整法
・中殿筋と小殿筋の役割と関連する症状
・中殿筋と小殿筋の調整(弛緩→ストレッチ→活性)
(担当:三本木講師)
三本木講師が先月取り上げた大殿筋に続き、今月は中殿筋と小殿筋の調整法を紹介。アプローチの流れは、筋肉の弛緩、ストレッチ、活性の順に構成されています。弛緩のためのインプットの施し方、ストレッチの方法、各筋肉をターゲットとした活性法が解説されています。
参加者のご要望にお応えする形で展開する『フリーレクチャー2』コース。
これまで皆さまが気づかなかった実践的なニッチな情報をお伝えすることで、皆さまの知識の隙間が埋まって、皆さまの引き出しの中にある知識が有機的に繋がっていくような場にしたいと思います。
皆さま、これからの『フリーレクチャー2』コースにぜひぜひご期待くださいませ!!!
※あらかじめテーマを決めて展開するセミナーではないのでレジメはございませんが、レクチャーの内容の要点を記した「セミナーメモ」がDVDに添えられます。
セミナーに参加できなかった皆さまは、ぜひDVDをご購入くださいませ。
大井 洋